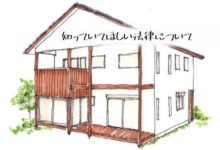こんにちは!作業着を7枚着てても寒くて震えてるみやしょうです!
先日初めて 地鎮祭 に参加してきました!地鎮祭とは工事を始める前に土地の神を鎮める儀式です。また土地を使用させてもらう許しを乞うためや、土地を清め工事の安全を祈願する儀式です。その他にも施主様、施工者、設計者の3者顔合わせや工事開始を近隣に知らせるという社会的な意味もあります。
まず地鎮祭を行うにあたって敷地内に 幄舎(あくしゃ)と呼ばれる仮小屋を組み立てます。寒さで体は固まっていましたが5人で30分程で組み立てられました!

幄舎を組み立てると 修祓(しゅばつ) という儀式をします。修祓とは、神を迎える前に神職さんにお祓いをしてもらい清めてもらうことです。お祓いをしてもらうのは参列者だけではなくお供え物にもしてもらいます。

修祓が終わると神にお供え物を供える 献饌之儀(けんせんのぎ) をします。

献饌之儀の次は 四方祓之儀(しほうはらいのぎ)という儀式です。これは敷地の四方と中央に米、塩、酒、半紙などを撒き、土地を清める儀式です。

四方祓之儀が終わると神職が式文を唱える 祝詞奏上(のりとそうじょう) をします。これが行われてやっと地鎮祭の主要な儀式に入ります。

祝詞奏上の次は 刈初之儀(かりそめのぎ) をします。刈初之儀とは斎砂(いみすな)と呼ばれる砂山に挿した笹を草に見立てて設計者が斎鎌(いみかま)で「えい、えい、えい」と掛け声をかけながら刈り取る動作をする儀式です。

刈初之儀に続けて 穿初之儀(うがちぞめのぎ) をします。これは施主様が敷地に見立てた砂山に斎鍬(いみくわ)を入れる動作をし、「えい、えい、えい」と掛け声を掛けます。

次に施工者が砂山に斎鋤(いみすき)を入れる動作をし、「えい、えい、えい」と掛け声を掛ける地曳之儀 (じびきのぎ)をします。

ここまでで修祓→献饌之儀→四方祓之儀→祝詞奏上→刈初之儀→穿初之儀→地曳之儀と儀式の名前や、斎鍬、斎鋤と使う道具を書いてきましたが、既に読み方分からないので復習も兼ねて、地鎮祭で使う道具をまとめてみました!

まとめてみてもどの道具を何の儀式のときに使うか分からない(*^▽^*)
次に 玉串奉奠(たまぐしほうてん) という儀式をします。これは玉串を祭壇の神前に供える儀式です。この儀式は参列者全員行うので僕もしてきました!
本来はこの後に 神酒拝戴(しんしゅはいたい) という、神前に捧げたお酒を神職から頂戴し皆で頂く儀式がありますが今回はコロナ禍ということもあり割愛しました。
家を建てる前の大切な儀式なので参加できて良かったです!
今回は普段、生活していたら読むことのない漢字ばかりで疲れたと思いますが、最後まで読んで下さってありがとうございました!
穿初之儀 ← もう読めますよね?(´◉◞౪◟◉)