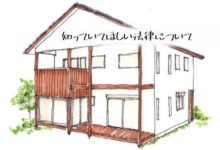「枝打ちから学んだこと」
山で木を育てる中で、「枝打ち」はとても大切な仕事です。
柱や床板に使われる“節のない美しい木材”をつくるためには、木が若いうちに枝を落とす必要があります。枝をそのままにしておくと、幹に節が残り、建材としては使いづらくなってしまうのです。
私の父は、その枝打ちの名人でした。梯子も使わず、木を抱きかかえるようにしてスルスルと登り、黙々と枝を落としていく。子供ながらに「なんであんなことができるんやろう」と驚きと尊敬のまなざしで見ていました。
私はというと、そんな器用にはいかず、いつも梯子を使って登っていました。枝打ちの道具は鉈(なた)です。木の上でバランスをとりながら、ひとつずつ枝を切り落としていく作業は、見た目以上に神経を使います。
ある日、作業中にへまをして、鉈で左手の指を切ってしまったことがありました。そのときはなぜか痛みをあまり感じず、気づけばそのまま作業を続けていました。でも、木から降りた瞬間、ズキンと強烈な痛みが走り、「ああ、これはやってしまったな」と思いました。
今思えば、あの頃の経験が、木と向き合うことの怖さや、慎重に仕事をすることの大切さを教えてくれたように思います。枝打ちは、見た目を整えるためだけではなく、「将来の価値」をつくる作業でもあります。
家づくりも同じです。目には見えない部分に手間をかけることで、将来の暮らしやすさ、美しさにつながっていく。今も私は、あの枝打ちの山の中で感じた緊張感を忘れずに、一棟一棟に心を込めて、丁寧な住まいづくりを続けています。